
副業がバレないようにするには?バレる原因についても徹底紹介


 目次
目次

2017年に閣議決定された働き方改革で副業が推進されたことから、副業可能な会社も増えてきました。
しかし、就業規則で副業を禁止している会社もまだまだ多いのが現実です。
そこでこちらの記事では、副業禁止の会社で副業がバレてしまう原因やバレないようにする方法から、バレにくいおすすめの副業まで紹介していきます。
 本来、アルバイトやパートとして別の場所に出勤する場合を除いて、周囲の人に副業がバレてしまうということは少ないでしょう。
しかし、在宅での副業でもバレることはあります。
ここではどういったときに、副業をしていることが同僚や会社にバレてしまうのかについて見ていきましょう。
本来、アルバイトやパートとして別の場所に出勤する場合を除いて、周囲の人に副業がバレてしまうということは少ないでしょう。
しかし、在宅での副業でもバレることはあります。
ここではどういったときに、副業をしていることが同僚や会社にバレてしまうのかについて見ていきましょう。
 ここまで副業がバレる原因について、代表的なものを3つご紹介してきました。
では、どのような工夫をすれば、バレずに副業をすることができるのでしょうか。
ここまで副業がバレる原因について、代表的なものを3つご紹介してきました。
では、どのような工夫をすれば、バレずに副業をすることができるのでしょうか。
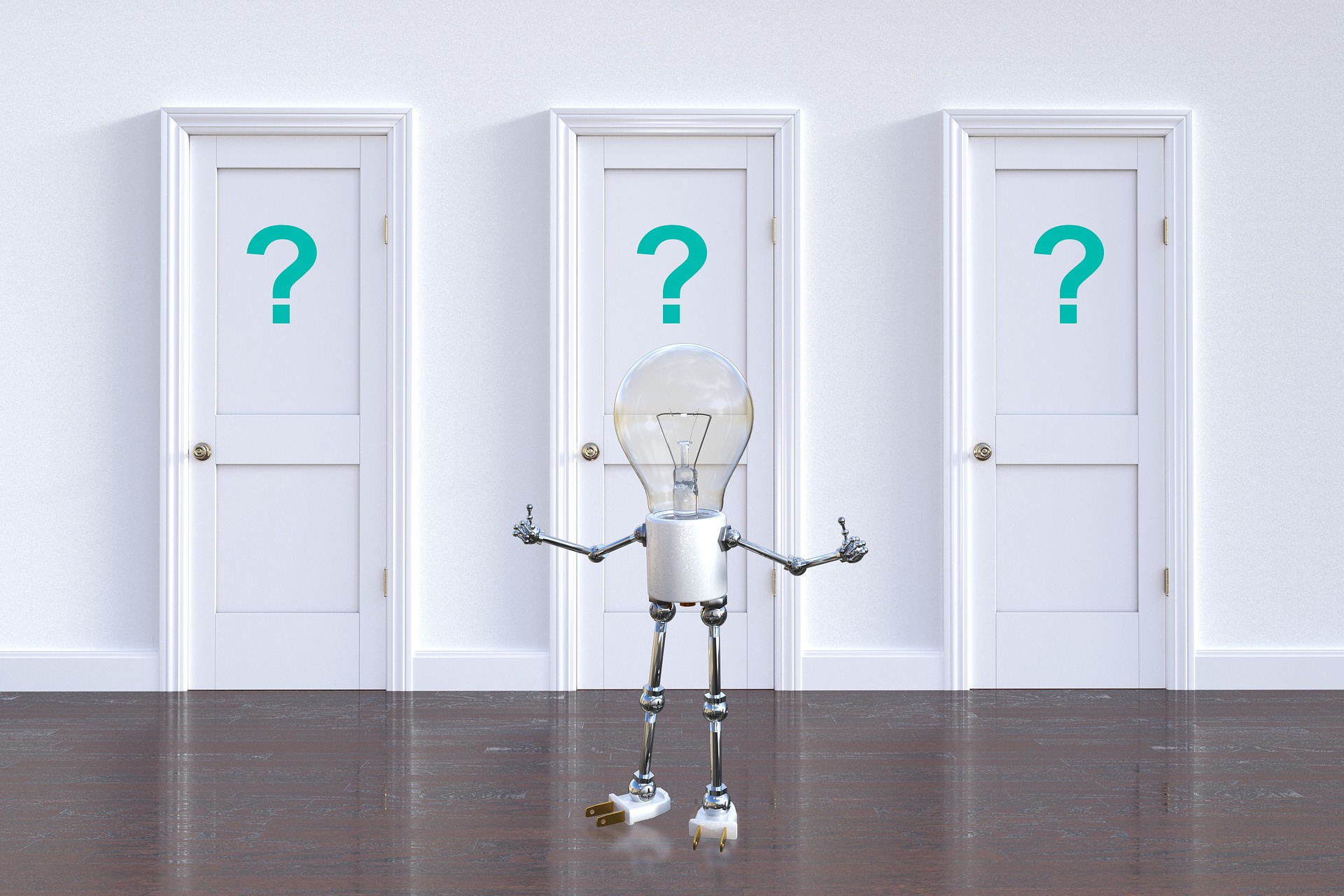 ここまで勤務先の会社に副業をバレないようにするための対策についてお伝えしてきましたが、そもそもなぜ副業をすることに問題があるのでしょうか。
たしかに公務員は、国家公務員法 (e-Gov法令検索)の第103条によると、副業はできないことになっています。
しかし会社員には副業を禁止する法律はありません。
ここからは、なぜ副業を禁止する会社があるのかについて考えていきましょう。
また副業をするに当たってどのようなことに注意すべきかについてもお伝えいたします。
ここまで勤務先の会社に副業をバレないようにするための対策についてお伝えしてきましたが、そもそもなぜ副業をすることに問題があるのでしょうか。
たしかに公務員は、国家公務員法 (e-Gov法令検索)の第103条によると、副業はできないことになっています。
しかし会社員には副業を禁止する法律はありません。
ここからは、なぜ副業を禁止する会社があるのかについて考えていきましょう。
また副業をするに当たってどのようなことに注意すべきかについてもお伝えいたします。
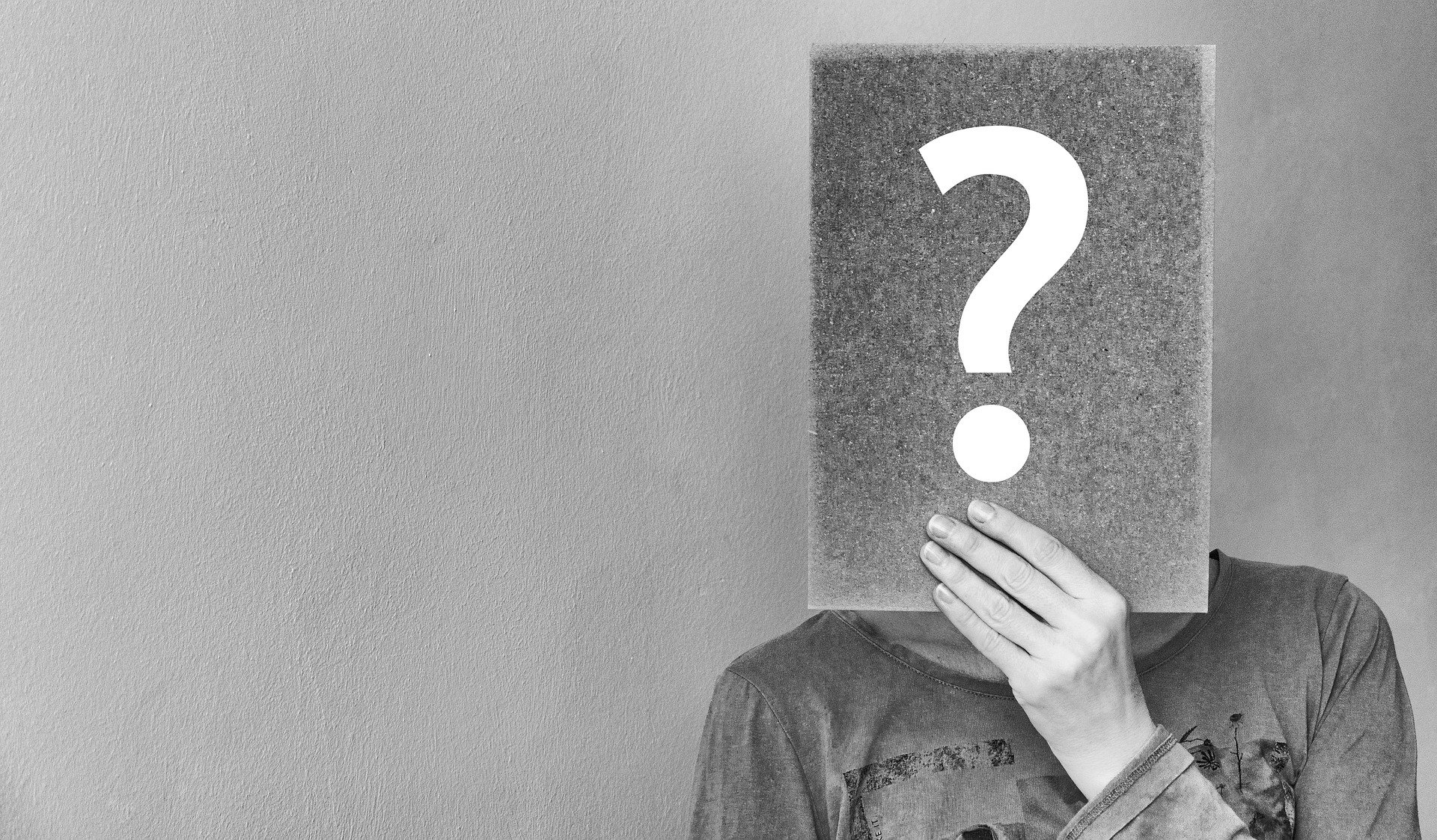 本業の勤務先にバレにくく、自己管理しやすい副業にはどのような特徴があるのでしょうか。
本業の勤務先にバレにくく、自己管理しやすい副業にはどのような特徴があるのでしょうか。
副業がバレる3つの原因
 本来、アルバイトやパートとして別の場所に出勤する場合を除いて、周囲の人に副業がバレてしまうということは少ないでしょう。
しかし、在宅での副業でもバレることはあります。
ここではどういったときに、副業をしていることが同僚や会社にバレてしまうのかについて見ていきましょう。
本来、アルバイトやパートとして別の場所に出勤する場合を除いて、周囲の人に副業がバレてしまうということは少ないでしょう。
しかし、在宅での副業でもバレることはあります。
ここではどういったときに、副業をしていることが同僚や会社にバレてしまうのかについて見ていきましょう。
周囲の人間に話してしまう
まず1番シンプルですが、会社の同僚など周囲の人にうっかり話をしてしまうのがバレる原因の1つとして挙げられます。 どんなに信頼しあっている仲だったとしても、会社の同僚や知人には絶対に話さないように気をつけましょう。 万が一副業でたくさん収入を得て、誰かに自慢したいと思ったとしてもグッと我慢することでバレずに副業を続ける秘訣です。住民税の金額の変化
バレてしまう原因の2つ目は住民税の金額が変わることです。 一般的に会社に勤めてそこから給与をもらっている場合、住民税は給与から天引きされる形です。 しかし副業の確定申告を行うことで、自治体から勤務先の会社に通知される源泉徴収税額が、副業の収入も含めたものになります。 会社が支払っている給与のわりに住民税が高いと、会社に副業をしていることがバレる原因となります。SNSやWEBサイトなどから
周囲の人に話してしまうのと同じようにうっかりしやすいのが、SNSです。 本名でなく匿名で使用していたとしても、勤務先の会社の人と繋がっていたり、勤務先やその周辺で撮影した写真をSNSに上げていたりすると、特定される可能性が高くなります。 その特定されたSNS上で副業をしていることについて書き込んでしまうことで、勤務先やその同僚からバレてしまうことがあります。 また、最近はクラウドソーシングを使用した副業も多くありますが、クラウドソーシングサイトの登録情報から特定され、そこからバレてしまうこともあります。 ブログでアフィリエイトによる収入を得る場合も同じことが言えます。 そのためWebを利用した副業を行う際は、投稿内容だけでなく写真や登録情報にも十分注意して活用する必要があります。副業がバレないようにするには?
 ここまで副業がバレる原因について、代表的なものを3つご紹介してきました。
では、どのような工夫をすれば、バレずに副業をすることができるのでしょうか。
ここまで副業がバレる原因について、代表的なものを3つご紹介してきました。
では、どのような工夫をすれば、バレずに副業をすることができるのでしょうか。
副業のための会社を設立する
まず1つ目は、副業のために自分で会社を設立することです。 会社を設立して法務局に登記した段階で国税庁の「法人番号公表サイト」に掲載されても、国税庁のサイトには、代表取締役の名前や従業員の名前が掲載されることはありません。 ただ、社会保険料に関して1つ問題があります。 自分で会社を設立して他に従業員がいなかったとしても、その会社で社会保険に加入しなければなりません。 もちろん本業で勤めている会社でも社会保険に加入しているはずです。 1人で複数の会社の社会保険に加入した場合、年金事務所から社会保険料に関する通知が会社に届いてしまいます。 1社でのみ社会保険に加入している場合にはこのような通知が届くことはないため、会社に社会保険料に関しての通知が届くことで、どこか別の会社でも給与をもらっていることがバレてしまうのです。 それではここからは勤務先の会社にバレずに、会社を設立して副業をする方法についてお伝えいたします。 まず、自分が設立した会社で自分が働いていることにしないのが大きなポイントです。 実際に会社を設立したり、業務を行うのが自分自身だとしても、給与を受け取るのは自分の家族などにしておきましょう。 副業用に設立した会社から給与を受け取ることがなければ、本業の勤務先の会社に社会保険料に関する通知が届くこともありません。 家族が給与を受け取るようにできなければ、親しい友人にお願いしても問題ありませんが、トラブル回避の観点で、家族以外はあまりおすすめできません。 代わりに給与を受け取ることができる家族や、お願いできる親しい友人がいない場合は、給与という形で報酬を受け取らず、会社に利益を留保すると良いでしょう。 社会保険料は給与に対して発生するため、会社に留保することで社会保険料がかからなくなります。 このような形を取ることで、本業の勤務先に通知書が届いてバレてしまうのを防ぐことができます。 ただし、副業で得た報酬を会社に留保することで法人税がかかりますので、その部分では注意が必要です。不用意に周囲の人間に話さない
ここまでお話ししてきたように、注意を払って会社を設立しても、うっかり周囲の人に話してしまったら元も子もありません。 会社の同僚でなければバレることはないだろうと考えたり、地元の友人であれば問題ないだろうと考えてしまいがちではないでしょうか。 人はどこで繋がっているか分からないので、勤務先に隠して副業をしている場合は家族以外には話さないことをおすすめします。住民税を自分で納付する
副業がバレる原因の1つとして、住民税の金額の変化を挙げました。 会社に勤務している場合の住民税の支払い方法は「特別徴収」という形になりますが、副業の確定申告をする場合は、住民税の支払い方法で「特別徴収」を選択せず、「普通徴収」を選択しましょう。 自分で納付する形にすることで、勤務先に住民税の金額がバレることがなくなります。副業をしたら何が問題なの?
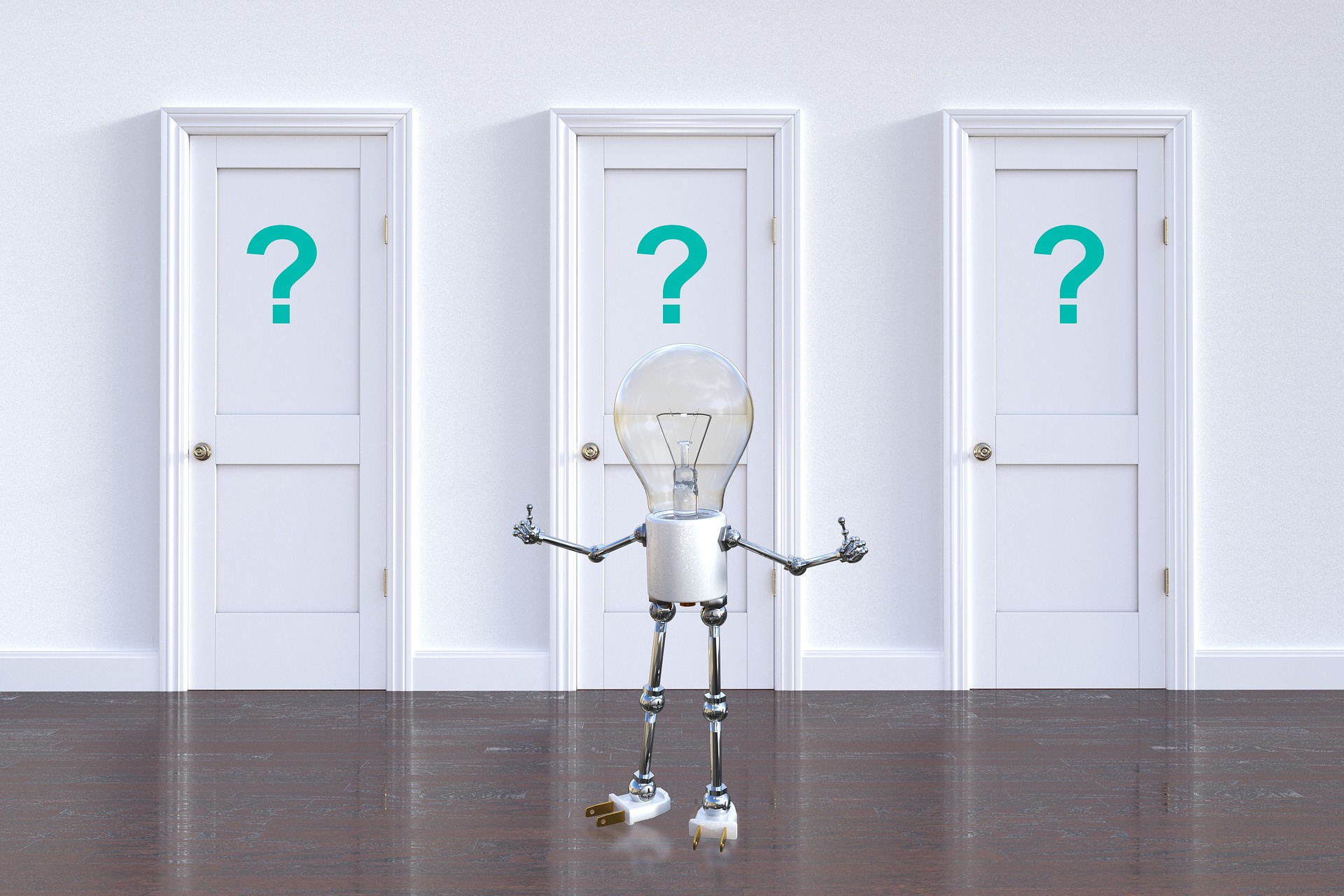 ここまで勤務先の会社に副業をバレないようにするための対策についてお伝えしてきましたが、そもそもなぜ副業をすることに問題があるのでしょうか。
たしかに公務員は、国家公務員法 (e-Gov法令検索)の第103条によると、副業はできないことになっています。
しかし会社員には副業を禁止する法律はありません。
ここからは、なぜ副業を禁止する会社があるのかについて考えていきましょう。
また副業をするに当たってどのようなことに注意すべきかについてもお伝えいたします。
ここまで勤務先の会社に副業をバレないようにするための対策についてお伝えしてきましたが、そもそもなぜ副業をすることに問題があるのでしょうか。
たしかに公務員は、国家公務員法 (e-Gov法令検索)の第103条によると、副業はできないことになっています。
しかし会社員には副業を禁止する法律はありません。
ここからは、なぜ副業を禁止する会社があるのかについて考えていきましょう。
また副業をするに当たってどのようなことに注意すべきかについてもお伝えいたします。
会社が労働時間を管理できない
まず労働時間についてですが、1人あたりの労働時間は労働基準法で決められています。 法定の労働時間、休憩、休日 ・使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 ・使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 ・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 引用元:労働時間・休日 (厚生労働省) この労働基準法で定められた労働時間は、「労働基準法 (e-Gov法令検索) 」の第38条によると、本業としての勤務時間だけでなく、本業と副業を通算した勤務時間に適用されるようです。 勤務先は、社員の勤務時間を法定の労働時間を超えないように管理する必要があります。 副業の勤務時間が決まっていて、本業の会社も社員の副業に関する管理体制が整っていれば、労働時間の管理も問題ありません。 しかし中小企業など、そのような管理体制がない場合において、副業をしている社員の労働時間の管理は困難です。 また社員が副業をしていると、法定の労働時間を超えないように、本業の勤務先が残業時間を調整する必要が出てくる場合もあるでしょう。 業務が立て込みやすい月末や年末、繁忙期に労働時間を調整するのは、会社に損害を与えかねません。 そのため、就業規則で副業が禁止されている会社で勤務しながら副業をする場合は、本業の業務内容や時期を考慮して、副業の勤務時間を調整することで労働時間を自分で管理するようにしましょう。会社の機密情報の漏洩につながる
次に、会社の機密情報の漏洩についてです。 たとえアルバイトやパートなどの非正規社員でも、会社と雇用契約を結んでいるほとんどの場合、会社と秘密保持契約書を締結しているはずです。 秘密保持契約は、会社がもつ秘密情報を他者にどの程度開示して良いか明確に定め、その情報を秘密に保持する方法や使用目的、試用期間、返還方法などを取り決めるために締結する契約です。 副業を認めている会社でも、多くの場合は会社からの許可が必要で、会社が定めた範囲外の副業をするのは禁止されています。 たとえば本業の会社の競合にあたる会社で副業を行い、本業の会社で得た情報を副業先で共有してしまった場合は秘密保持契約の違反になります。 それだけでなく、本業の会社に大きな損害を与えてしまいかねません。 本業と似たような業務を行う方が負担も少なく、副業として成果も生み出しやすくはなりますが、秘密保持契約の内容をよく確認した上で違反にならない範囲で副業を行いましょう。本業の会社でのパフォーマンスが落ちる
会社が労働時間を管理できない場合は特に、自分では管理しきれずに空いた時間を全て副業の勤務時間にあててしまう人もいるのではないでしょうか。 それによって体調管理がしきれずに本業の遅刻や欠勤が増えてしまうことで、会社にとってデメリットになります。 実際に、兼業・副業に関する裁判例をまとめた厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン 参考資料2」によると、私立大学の教授が無許可で語学学校講師等の業務に従事し、講義を休講したことを理由に裁判が行われたこともあるようです。 この場合は解雇無効となったようですが、副業をすることで裁判に発展するようなことは、会社としても従業員としても避けたいところではないでしょうか。 これらのことから、会社に許可を得ずに副業をする場合も、本業の会社との秘密保持契約違反にならない範囲で、自分で労働時間や体調管理をしっかり行うことが大切です。バレにくい副業の特徴とは?
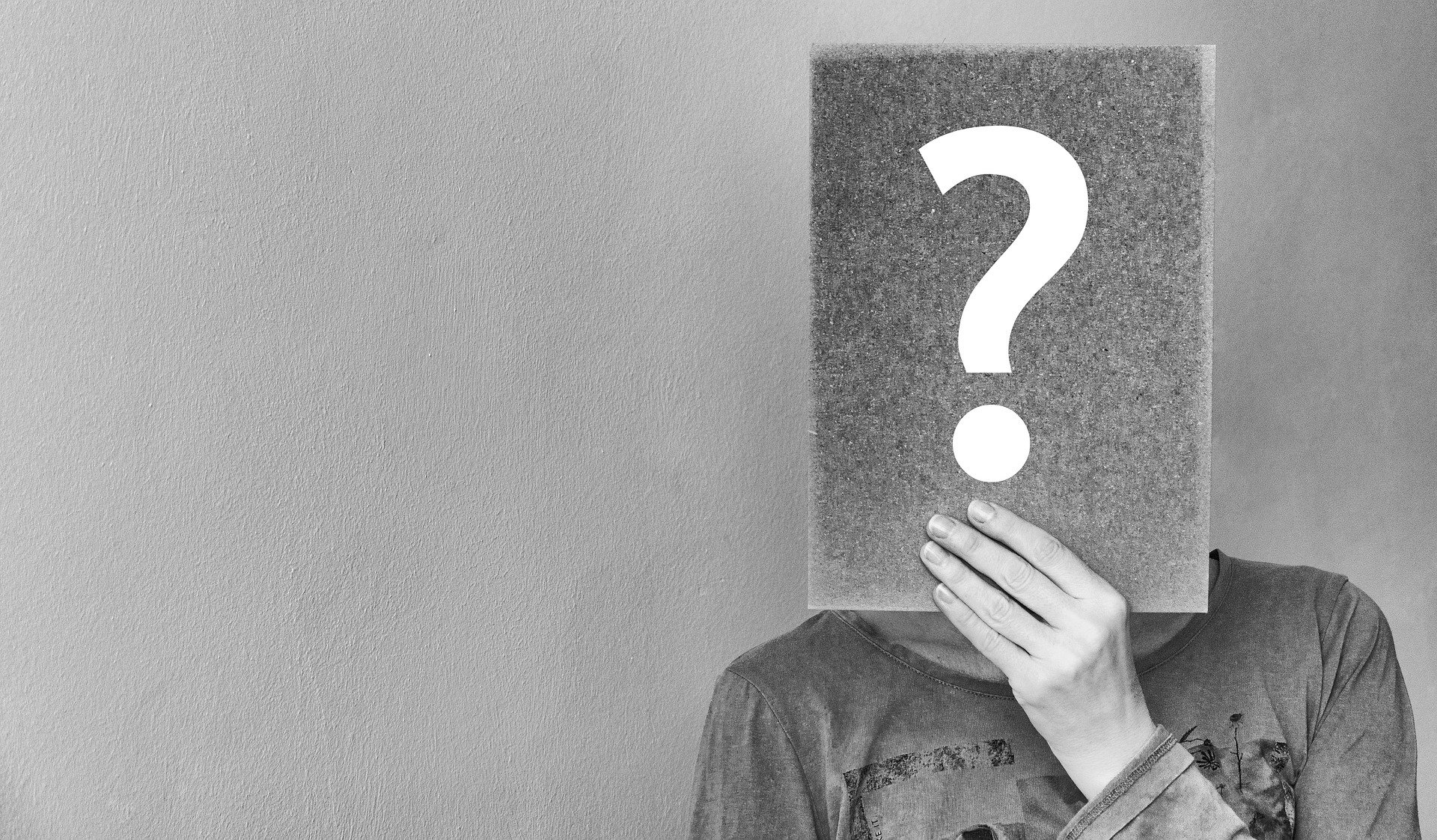 本業の勤務先にバレにくく、自己管理しやすい副業にはどのような特徴があるのでしょうか。
本業の勤務先にバレにくく、自己管理しやすい副業にはどのような特徴があるのでしょうか。









